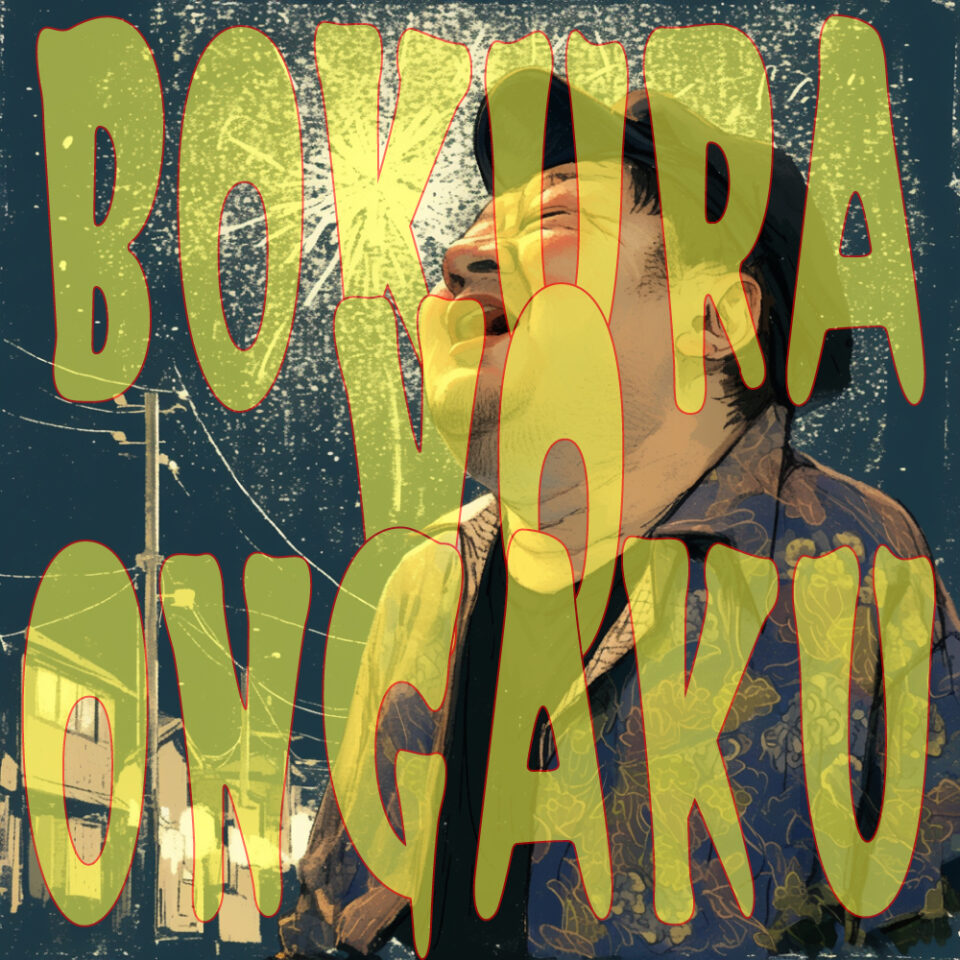しかし、物を語る上で。誰かに『それもあるかも』なんて思ってもらうのは大前提だと思うのです、なんてったって、物語を作る上で大事なのは 『共感力』 ですからね。
独創性なんてのは共感のその先に生まれてくるのです。
もちろん『凡人のオイラ』には理解ができない『天才』って奴もいるので、そんな奴らのロジックは論外としておきましょう。
天才を論外にするなんて不条理だと言われても仕方がないのです、なぜなら、今は不条理劇の話をしているのですからっ。
アレ?でも、『ゴドーを待ちながら』を書いたサミュエル・ベケットが天才だったら・・・。
まあ。。。いいか。
『天才』の定義は、また、いつか別のエッセイでお話することにしましょう。
では、とりあえずオイラの『物を語る物語』についての持論は。
明確な答えがないモノに対して生まれるのは好奇心だと思うのです、ただ、ソレに興味がないと深掘りなんてしてくれない訳で、興味を持ってもらう為の共感力は必要だと思うのです。
しかし、この考え方だと、不条理劇は人気があればある作品ほど、その作品の不条理自体が形式化されてしまい不条理とは程遠い存在になるのではないかと思うのです。
つまり有名な不条理演劇ほど、駄作になってしまう可能性が高いのではないかと思うのです。
でも、どうなんでしょう?もしかしたら、逆説的に考えたら「分かりすぎてしまう不条理」これが本当の不条理の皮肉なのかもしれませんね。
でもな~~~。
不条理を「分かりやすい」か「分かりにくい」で二分するのは、その本質を限定してしまうかもしれないし。。。
だとしたら。
不条理は「形式」ではなく、あくまで「意図」と「影響力」によって成立するものと考えるとした場合にはどうなるのかな?