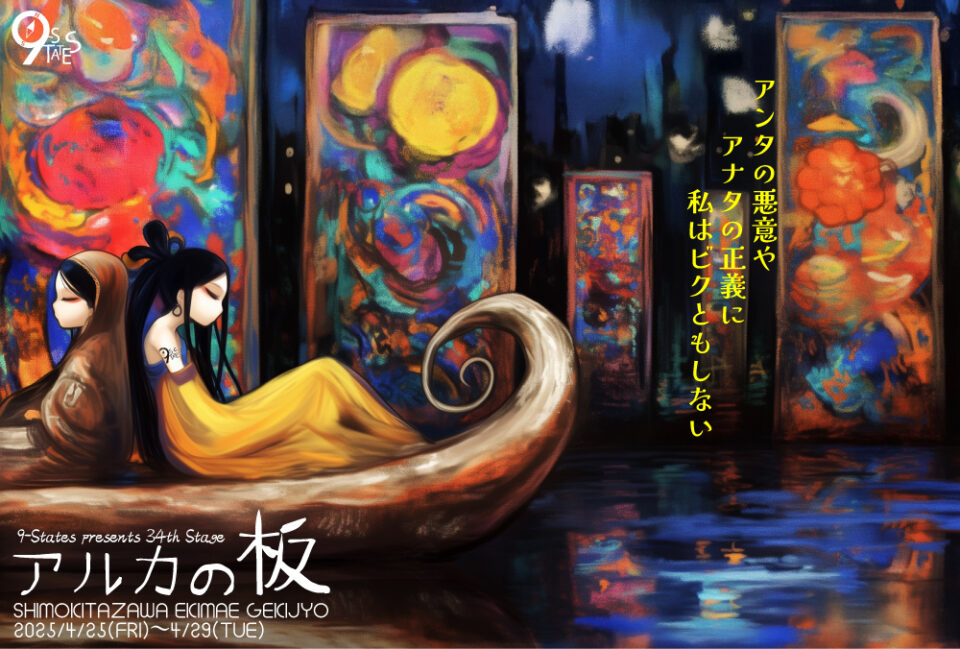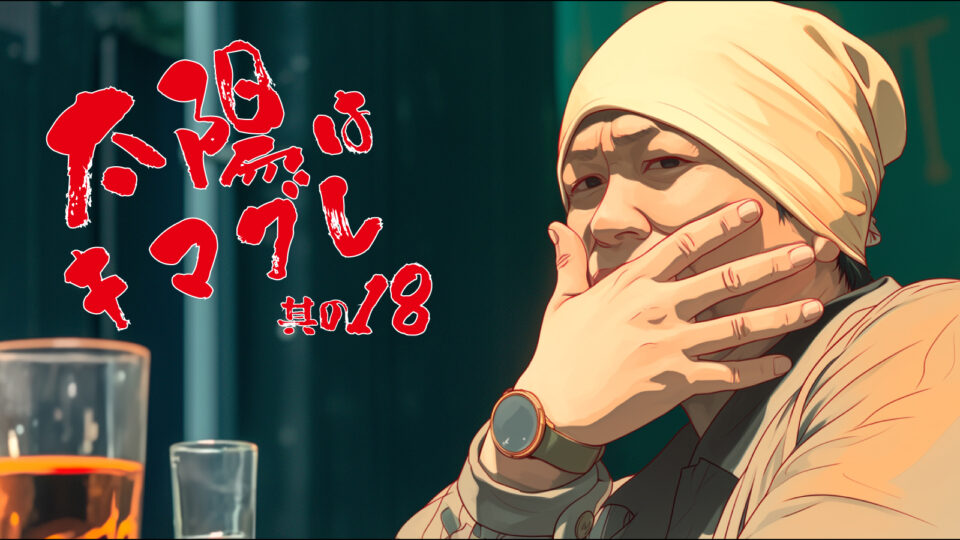物語なんてリアルとは程遠いのです。でも、それでいいのです、なぜなら、そこに夢があるのだから。
だからこそ『リアリティーと言う名の共感力』は追及しなきゃダメだと思うのです。
脚本家が本を書く時にどんな作業をしているかイメージできますか?
簡単な話で例えるならば、物語の中の時間って、リアル世界の「良いとこ取り」をされてるんです、なんと言っても、起承転結で描かれていますからね、話が進まない会話は物語が停滞する為、先に進めるように書かれているのです。
つまり、日常なら5時間かかるような会議があったとしても舞台上では5分くらいのシーンになるんです。
結構、無茶苦茶なことを、当たり前のようにやってるんです。
だって、ただの会議を5時間もみせられたらお客さんもたまったもんじゃないですからね、重要なポイントを違和感がないように纏められてるわけです。
ただ、演者の皆さんはソレを芝居で、さも、長時間の重要な会議があったようなインパクトを残さないといけない訳です。
いや~、役者さんは大変そうですね、ただ、ここは非常に重要ポイントです、おそらくテストに出ます。
つまり「舞台上」と「日常」の『時間感覚』は全く違うわけです。
なのに、いざ、会話劇をやる時って、やたらリアルに拘(コダワ)る役者が多いように感じるのです。
なんか逆に技術の押し売り的な『さも自然に喋ってるでしょ』みたいなことを見せつけてくるんだよね、そんなものはいらないのです。
全部が全部、同じテンポで会話してどうするんだいって話です。かったるくて見てられなくなります。
つまり『リアリティーが欲しい』って口にしているってことは、アナタの芝居は、作られた世界の中でズレてるぞってことなんですよね。
己の普通を押し付けて、逆に浮いてるぞっていう。
己の普通を勘違いして、悪目立ちしてるぞっていう。
周りが見えていなくて、自己中心的な芝居しかできてないぞっていう。
もちろん、キャラを作り過ぎて会話にならず浮いてしまう役者もいたりします。
つまり、舞台俳優たるもの舞台上の設定を落とし込んで世界観を掴み【普通】を探し、共有しなければならないのです。
皆さん、もうお気づきだと思いますが、この【普通】と言う【固定概念】が最も厄介なのです。
なぜなら『普通という名の固定概念』は人それぞれだからです。