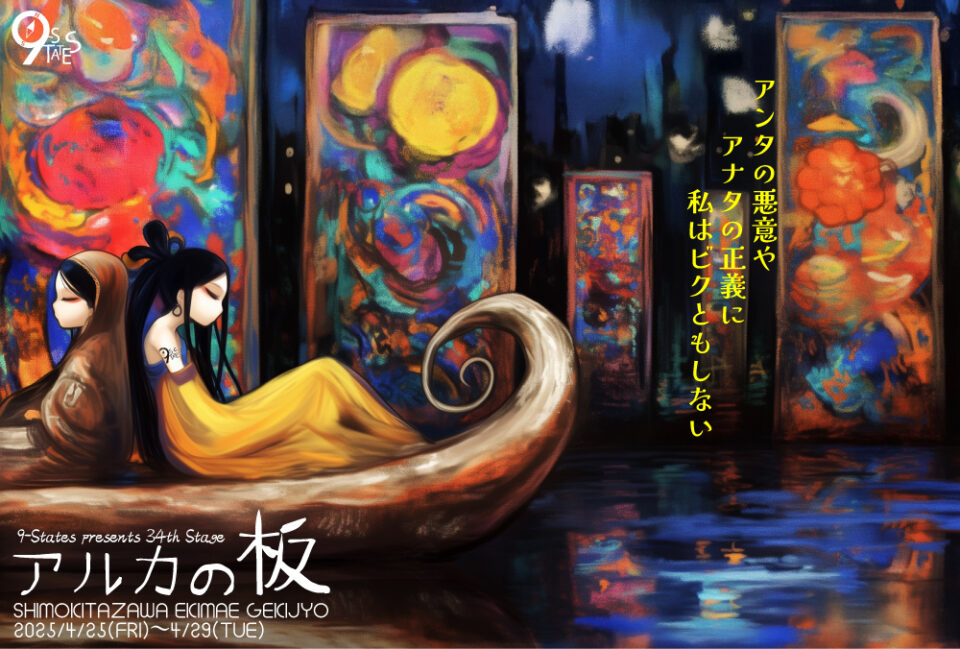一発撮りとかの映像とかでもない限り、芝居の稽古って基本はセッションだと思うんですよね、押付けでは自分の想像以上の芝居なんて生まれません、でも、今までやってきた経験とかで、にわか見世物にすることができたりしてしまう中途半端な役者さんは『自分はできる役者』と勘違いしてしまっていたりします。
自分だけのリアルって意外と貧困なのにね。
でも、納得できないんです、なんか嫌なんです、その人にとっては。
きっと、リアルリアル言ってる人ほど、自分で作り上げた「想像されたリアル」を追い求める傾向にあるような気がします。
おお、なんと言う矛盾。
それにね、真面目過ぎる役者にはこんな人もいたりするです。
お客さんは同じ金額を払っている訳だから、役者は、毎回毎回、10回芝居したら10回同じ芝居をしないといけない。
何を勘違いしているんだろう?とか思っちゃうんですよね、同じ芝居を提供することにバリバリの使命感を燃やしているのなら、映像やんなさいって話なんですけどね、大事なのは同じ芝居をやることじゃなくて、見世物としてのクオリティーをお値段以上で維持できるかなのにね。
リアル芝居と言う意味では、10回、同じ芝居をしようとしている時点で、リアルとはかけ離れてるからね。
まあ、似たようなことは、作家さんにも言えたりするんですけど。
やたら一言一句に拘って句読点の意味を想像して芝居してほしいとか言っちゃう作家さん。
20年、舞台の本を書いているオイラがこんなことを言うのは変だと思われるかもしれませんが。
あまり好きではありません。
あんまり強要しすぎて、ガチガチに決めるとロボットみたいになって、それこそ、役者なんて誰でもいいってことになりますよ。
それに、そんなに一言一句にこだわるなら、舞台の本は辞めて、小説を書いた方がイイんじゃないですかって、思っちゃうんだよな~。
若い頃、そんな発言をしたら、どっかの作家さんが「アナタは脚本に対して本気じゃないからそんなことが言えるんだ」と、えらく持論を押し付けてきたので。
そんな小さなことに拘ってるから、アンタの作品は面白くないんだよ。って、反論したら、ブチ切れられました。
いや、解るよ、コッチだって、何度も吐きながら必死で執筆活動した結果、台本が読めてない役者さんに「話が理解できないなら、まずは台本100回読んできてもらえますか?それで分からないなら1000回読んでもらえますか、そこに答えあるんで」みたいな、バカげた発言したことあるし。
これって、ただの八つ当たりだからね、本当、我ながら傲慢の極みです。
結局、何処まで行っても舞台って『総合芸術』なのにね。
作家も同じで一人のエゴを高々と掲げて、役者を本当の意味で『信頼』できないのなら、おそらく舞台作品には『向いてない』と思うんだよね。
ここで『信頼』と言うワードが出たのでオイラの演出論で大事にしていることを残しておきたいと思います。
オイラの演出の基本は、師匠である倉森勝利さんに教わった『役者は信頼してもいいけど信用するな』です。
どういう意味かまでは教えてくれなかったけど、オイラなりに実践しているつもりです。
あっ。なんか話が大きく脱線してしまいました。
それに、このままだと、色んな作家さんにも嫌われてしまいそうなので。
リアリティーの話に戻しましょう。