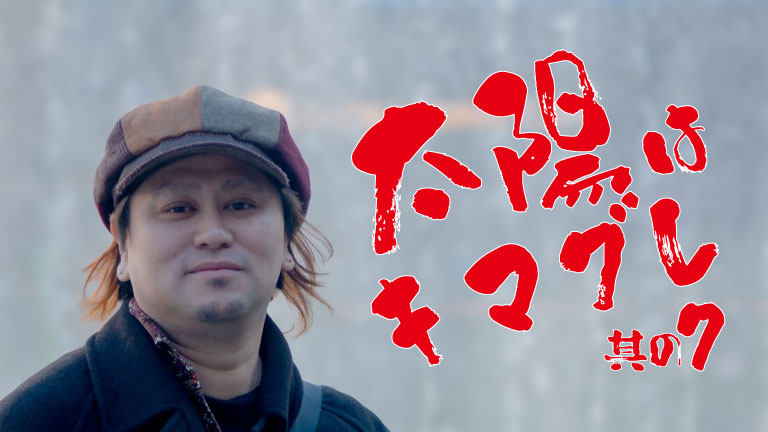スナック「海星」のカウンターで、足立はいつものように焼酎グラスを揺らしていた。その氷の音はママであるリリーにとって「さて、愚痴の時間ね」と思わせる合図でもあった。リリーはその足立をちらりと見ながら、手慣れた仕草でグラスを磨き続けている。
「ママさん、例の若い奴覚えてるだろ?九海丸にちょっといただけのやつ」足立が話を切り出す。 リリーは眉を少し上げながら、グラスを磨き続けた。「もちろん覚えてるわよ。でも何回目の話かは忘れちゃったわ」軽く返すその口調には、いつもの調子が含まれていた。
「効率が悪い、マニュアル化された資料がない。さらに『OJTはどうなってますか?』なんて言いやがってさ」足立は声を荒げてグラスを置き、その眉間には深いしわが刻まれている。「俺たち漁師が手取り足取り教えるとでも思ってんのか?見て、マネて、体で覚える。暗黙知」
リリーはその言葉に微笑みを浮かべながら、「時代が違うのよ。若い世代が求めるものとは交わらないってことね」と静かに返す。
「交わらないどころか、全部否定されてる気がするんだよな。こっちはこうやって何十年もやってきた。それを何も知らない若い奴に言われるとさ…なんか人生そのものを否定された気になるんだよ」足立は自嘲気味に笑いながら語った。
リリーが少し声を強めて言った。「だからってゲンコツはダメでしょう。ゲンコツは」
「それは剛の話だよ。俺はちゃんとそいつの味方もしてたんだぜ」足立は少し強めに返すが、すぐに声を落とす。
リリーは足立のグラスに視線を落としながら肩をすくめる。「じゃあ、どうして毎回同じ話ばかりするのよ?」
足立はグラスを一度見つめたあと、沈黙していたが、やがて軽く息をついた。「それは…まぁ、俺だって、若い奴の気持ちも、時代が変わってることも分かっちゃいるんだ。でもな、こっちだって守りたいものがある。古い漁師にも筋ってもんがあるんだ」
「SNSにさらされちゃった青山さんも災難だったけど、若い人たちを理解するのも筋の一部かもよ。足立さん」リリーが静かに微笑んで返す。その言葉に足立は一瞬口を開きかけるが、何も言わずにグラスを傾ける。カランと響く氷の音は、夜の静寂に溶け込んでいった。