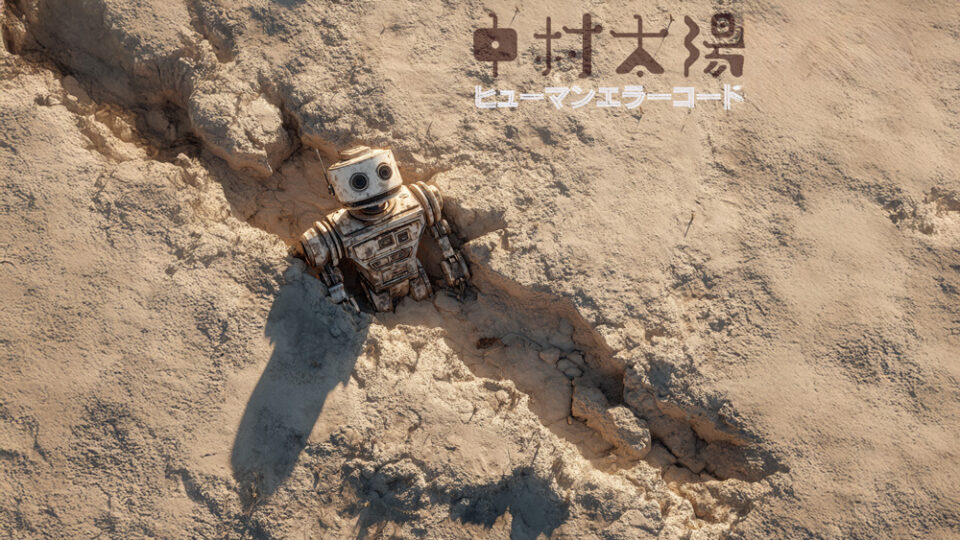その静けさを破ったのは、スナックの扉がきしむ音だった。重くて古びた扉がゆっくりと開き、誰かが店内に足を踏み入れた瞬間、カウンターで繰り広げられていたやりとりがぴたりと止まった。足立はグラスを持つ手を止め、リリーは磨いていたグラスを控えめに置く。そして振り返ると、扉の向こうから現れたのは鳥山だった。
「お邪魔するぜ!」鳥山がいつもの元気な声で挨拶する。あまりにも明るすぎて、リリーはそれが夜の空気にそぐわないと思うほどだったが、慣れたものだ。彼女はグラスを磨く手を止めないまま軽く目を上げただけで、「いらっしゃい」と微笑む。
カウンターにたどり着く前に、鳥山の目がまず足立に向かう。「お、ペイちゃんもいるじゃん。珍しいな、また憂鬱そうな顔してるな?」そう言いながら彼はカウンターの椅子を引き、どさりと座り込む。その動作は、まるでここが自分の居場所であるかのように自然だ。
足立はグラスを置き、半分目を閉じたような視線で鳥山を見やる。「お前、よくそんな明るさを保てるな。そろそろ港に太陽として就職したらどうだ?」
「その点、ペイちゃんはすっかり月だな。いつもどこか陰があるもんな」と、鳥山は楽しげに返す。鳥山がカウンターに座るやいなや、スナック「海星」の中はあっという間に彼のテンポに巻き込まれた。それまで微妙な空気を漂わせていた足立、いや、「ペイちゃん」と呼ばれる男も、思わず顔をしかめた。
「トオル、相変わらずだな。そんなに元気が余ってんなら、港の網でも直してくれよ」足立が軽く皮肉を込めて言うと、鳥山はにやりと笑った。
「ペイちゃん、それは無理な相談だ。俺が網を直すくらいなら、野菜でも持っていって柚ちゃんに手を貸した方がまだマシだよ」鳥山は肩をすくめながら、いつもの調子で応じた。その口ぶりには、彼が最近どれだけ事務所に顔を出しているかを誇るニュアンスが微かに含まれている。
リリーがそれを聞きながら微笑みを浮かべ、「まったく、どっちもどっちね。あの事務所にちょっかい出して、柚ちゃんやお母さんの花楓さんを困らせてるんじゃないでしょうね?」と、グラスを磨く手を止めずに言った。
鳥山が首を横に振り、「いやいや、困らせるどころか助けてるさ。出荷できない野菜を持って行って、代わりに混獲の魚をもらってるんだ。持ちつ持たれつってやつだろ?」と得意げに言う。
リリーがふと手を止め、鳥山に目を向けた。「じゃあ、花楓さんが倒れたのは知ってるの?」